マンションやオフィスビルなど、多くの建物で使われている「受水槽」と「貯水槽」。名前は似ていますが、実はその役割や設置基準、構造には大きな違いがあります。水道水を安全に使用するためには、これらの違いを正しく理解することが大切です。
この記事では、受水槽と貯水槽の違いから、設置基準、仕組み、そして欠かせない清掃管理まで、専門知識をわかりやすく解説します。建物管理や水回りに関わる方はもちろん、自分の住むマンションの給水システムに興味のある方にもおすすめの内容です。

受水槽と貯水槽の違いとは?基本的な定義を解説
「受水槽」と「貯水槽」、どちらも水を貯める設備ですが、その役割は明確に異なります。まずは基本的な違いから見ていきましょう。
貯水槽とは?
貯水槽は水を貯める設備全般を指す総称です。様々な種類の水槽を包括する広い概念と言えるでしょう。具体的には「受水槽」「高置水槽(高架水槽)」「貯湯槽」などが貯水槽に含まれます。設置場所や用途によって呼び名が変わる点が特徴的。地上や地下に設置される水槽、屋上に設置される水槽、お湯を貯めるための水槽など、多岐にわたります。
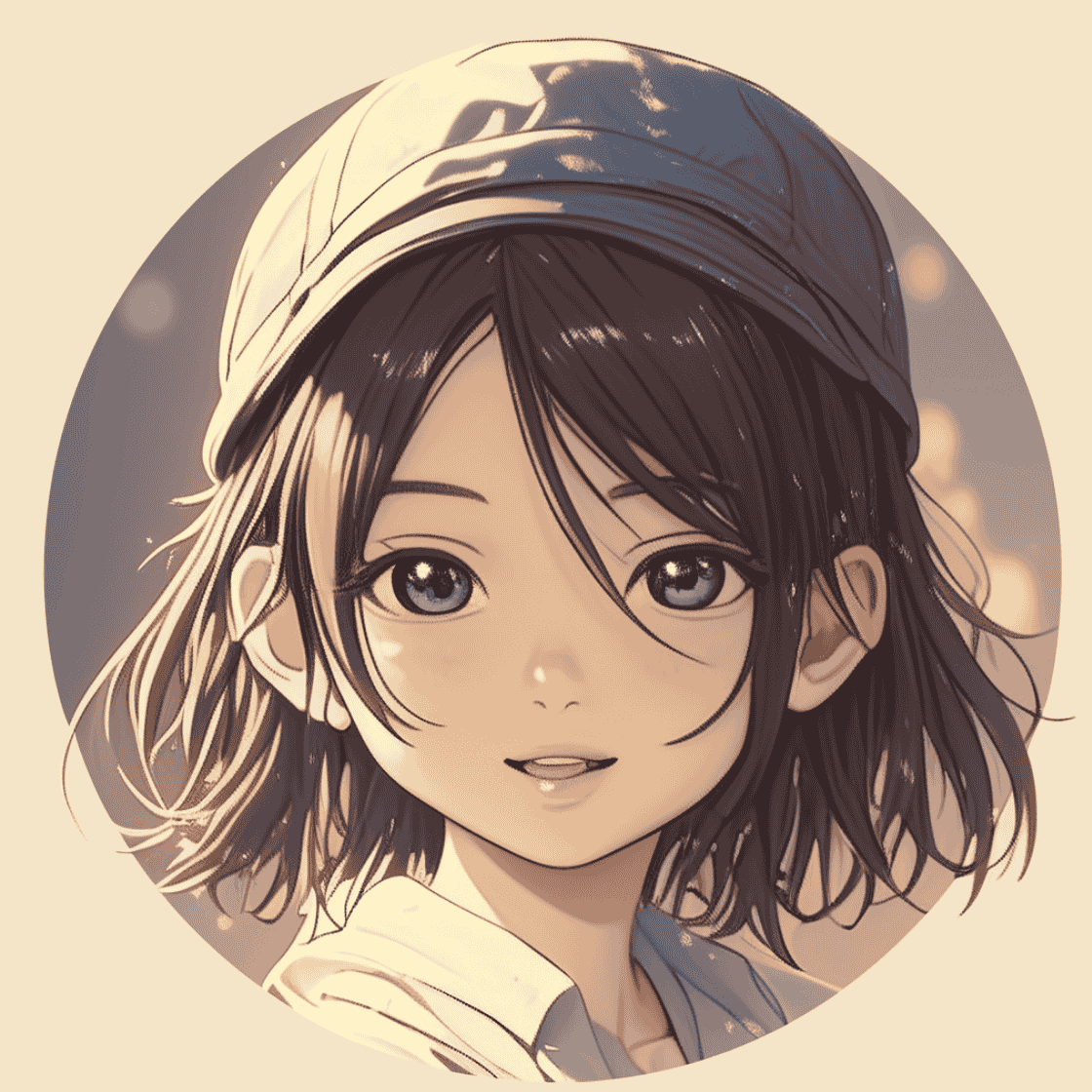
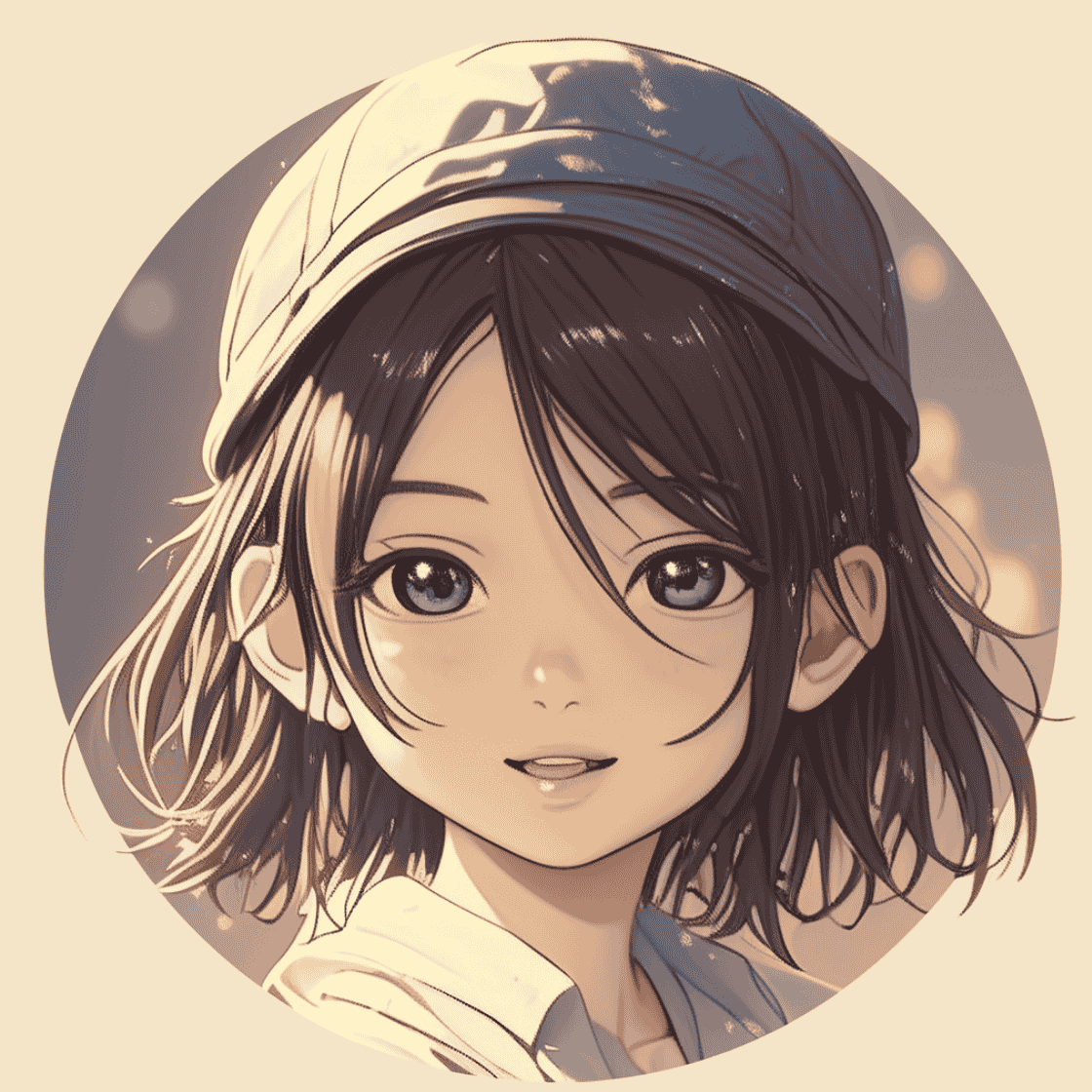
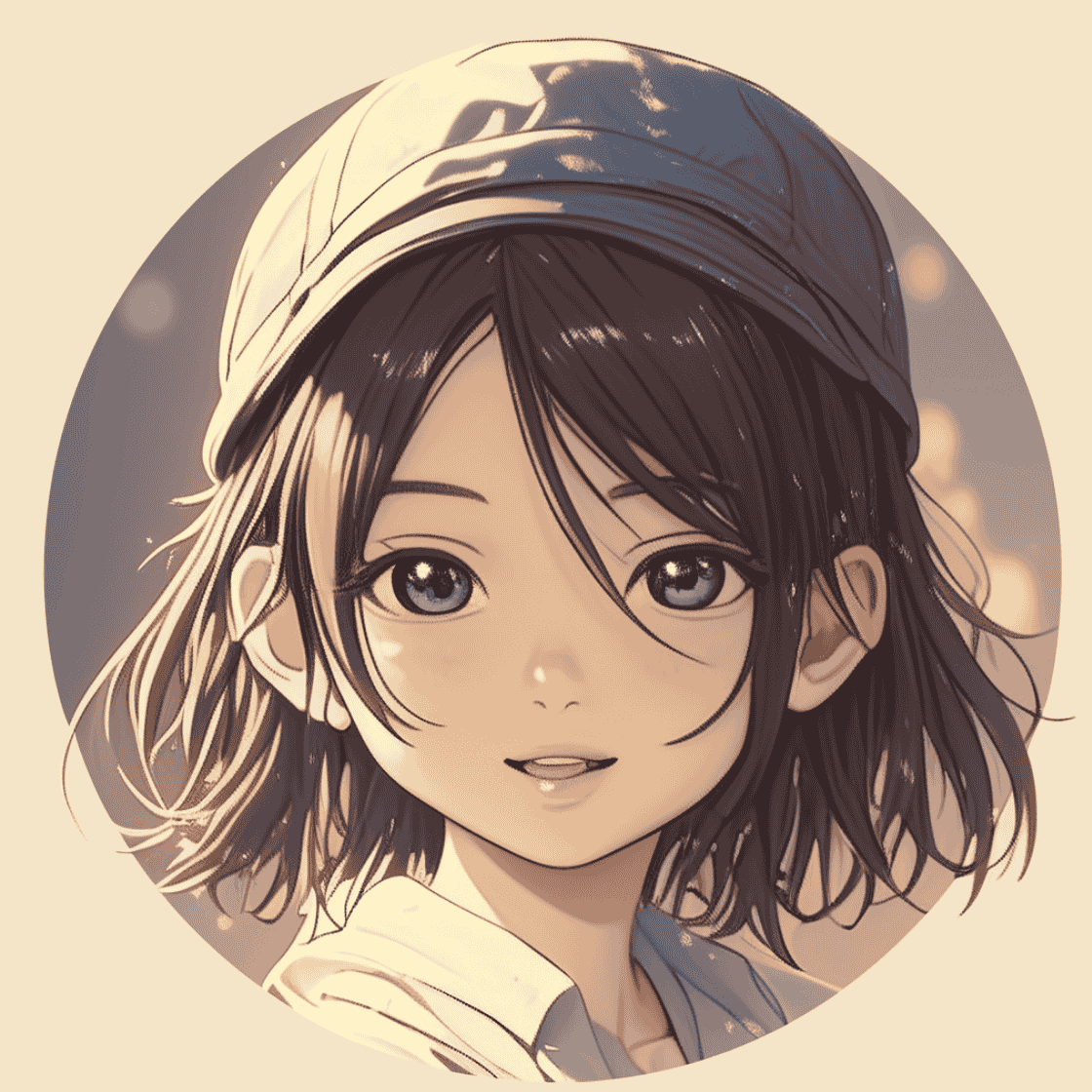
受水槽とは?
対して受水槽は、特に「水道水」を受け入れて貯めておくための設備を指します。水道本管からの水を一時的に貯留し、建物内に安定して給水するための重要な役割を担っています。多くの場合、建物の地下や1階部分に設置され、ポンプを使って上階に水を送るシステムの一部となっています。
両者の最も大きな違いは、「貯水槽」が水を貯める設備全般を指す総称であるのに対し、「受水槽」はその一種で、特に水道水のための設備であるという点です。例えるなら、「乗り物」と「自動車」のような関係と言えるかもしれません。



貯水槽と受水槽の違いまとめ
- 水道本管から飲用水を受け入れる特定の水槽
- 主に建物の地上階または地下に設置
- 安定した水圧・水量の確保が目的
- 10㎥超は年1回以上の清掃が法律で義務付け
- 6面点検ができるように設置が必要
- 水を貯める設備全般を指す総称
- 受水槽、高置水槽、貯湯槽などを含む広い概念
- 様々な種類の水(水道水、雨水、工業用水など)を貯留
- 用途に応じて設置場所や管理基準が異なる
- 用途に合わせた水の貯蔵が主目的
| 比較項目 | 受水槽 | 貯水槽 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 貯水槽の一種 | 受水槽、高置水槽、貯湯槽などを含む広い概念 |
| 主な設置場所 | 建物の地上階または地下 | 地上、地下、屋上など様々 |
| 貯める水の種類 | 飲用可能な水道水 | 水道水、雨水、工業用水など目的により様々 |
| 主な目的 | 建物内への安定給水、水圧調整 | 用途に応じた水の貯留(飲用、農業用など) |
| 清掃義務 | 容量10㎥超は年1回以上の清掃が法律で義務付け | 用途により異なる(飲用水の場合は受水槽と同様) |
| 管理責任者 | 建物の所有者または管理者 | 設備の所有者(用途により異なる) |
| 設置基準 | 6面点検可能な設置が必要 | 用途に応じて基準が異なる |
受水槽の設置基準について知っておきたいこと
受水槽の設置には、建築基準法をはじめとする様々な法律や規則によって厳格な基準が定められています。ここでは、主な設置基準について解説します。
設置場所の基準
受水槽は6方向からの目視点検(6面点検)が可能なように設置する必要があります。具体的には、受水槽の周囲に60cm以上のスペースを確保することが求められるのです。これは、定期的な点検や清掃を効率的に行うためのもの。設置場所を決める際の最重要ポイントと言えるでしょう。
また、建物の躯体(くたい)として受水槽を使用することは禁止されています。これは、躯体として使用すると点検が困難になり、水質管理に支障をきたす恐れがあるためです。



構造に関する基準
受水槽には、清掃を断水せずに行えるように2基以上設置するか、内部に仕切りを設ける必要があります。これは、一方の槽を清掃している間も、もう一方の槽から水の供給を続けられるようにするための工夫です。水は生活に欠かせないものなので、供給の継続性を確保する重要な基準となっています。
さらに、天井と底には1%以上の勾配をつけることが求められます。これは水の流れをスムーズにし、汚れの堆積を防ぐための設計。小さな工夫ですが、水質維持にとって大切な要素です。
マンホール(点検口)については、防水パッキンと鍵を備え、直径60cm以上のサイズにすることが基準とされています。これは、点検や清掃作業を行う人が安全に出入りできるようにするためのものです。
受水槽の仕組みを図解で理解しよう
受水槽を使った給水システムには、主に3つの方式があります。それぞれの特徴と仕組みを解説します。
高置水槽式の仕組み
最も一般的なのが「高置水槽式」です。この方式では、まず受水槽に水道本管からの水を貯め、そこからポンプで建物の屋上などに設置された高置水槽へと水を汲み上げます。そして高置水槽から自然落下(重力)の力を利用して、各階の蛇口へと水を送り届けるのです。
この方式の最大のメリットは、停電時でも高置水槽に貯められた水の分だけは使用できるという点。災害対策としても優れた方式と言えるでしょう。反面、屋上に重い水槽を設置するため、建物の構造強度が必要となります。



その他の給水方式
他にも「ポンプ直送式」と「圧力水槽式」があります。ポンプ直送式は受水槽からポンプの力で直接各階へ水を送る方式。シンプルな構造ですが、停電時には水が使えなくなるというデメリットがあります。
圧力水槽式は、小型の圧力タンクを使って水圧を安定させる方式です。設置スペースが限られる場合などに採用されることが多いです。
受水槽の構造図を詳しく見てみよう
フロー管
- 流入管:水道本管からの水を受水槽へ導く配管
- 水位制御弁:水槽内の水位を一定に保つバルブ
- マンホール:点検・清掃用の出入口(直径60cm以上)
- 通気管:水位変動時の圧力調整用
- オーバーフロー管:水位制御弁故障時の排水管
- 揚水管:水槽からポンプへ水を送る管
- 排水管:清掃時などに水を抜く管
- 中仕切り:清掃時も断水せずに作業できるようにする仕切り
受水槽の構造は細部にわたって緻密に設計されています。主要な部分とその役割について解説します。
受水槽の主な構成要素
受水槽には、様々な部品や設備が組み込まれています。その主なものは以下の通りです。
- 流入管(給水管):水道本管からの水を受水槽へ導く配管
- 水位制御弁:水槽内の水位を一定に保つためのバルブ
- マンホール:点検や清掃のための出入り口
- オーバーフロー管:水位制御弁の故障時に水があふれるのを防ぐ管
- 排水管:清掃時などに水を抜くための管
- 通気管:水位変動時の圧力調整のための管
- 揚水管:水槽からポンプへ水を送るための管
これらの部品が適切に機能することで、安全で清潔な水の供給が可能になるのです。



構造設計の工夫点
受水槽の構造には、水質を保つための様々な工夫が見られます。例えば、水の滞留を防ぐために底部に勾配をつけたり、排水溝を設けたりしています。また、外部からの汚染物質の侵入を防ぐために、マンホールには密閉性の高い二重蓋が使用されることが多いです。
水の循環を良くするための整流板の設置や、流入管と揚水管を対角線上に配置するといった工夫も一般的。これらの細部への配慮が、水質の維持につながっているのです。
受水槽と飲み水の関係について
受水槽を使用している建物の水は、水道本管から直接供給される水と比べて品質に違いがあるのでしょうか?この点について解説します。
受水槽の水は飲めるの?
結論から言えば、適切に管理されている受水槽の水は、水道本管からの水と同様に安全に飲用できます。定期的な点検や清掃が行われていれば、水質の差はほとんどないと考えて良いでしょう。
ただし、これは適切な管理が前提となります。受水槽から利用者の蛇口までは、建物の所有者や管理者が責任を持って管理する必要があります。管理が不十分だと、水質の劣化や細菌の繁殖などの問題が生じる可能性があるのです。
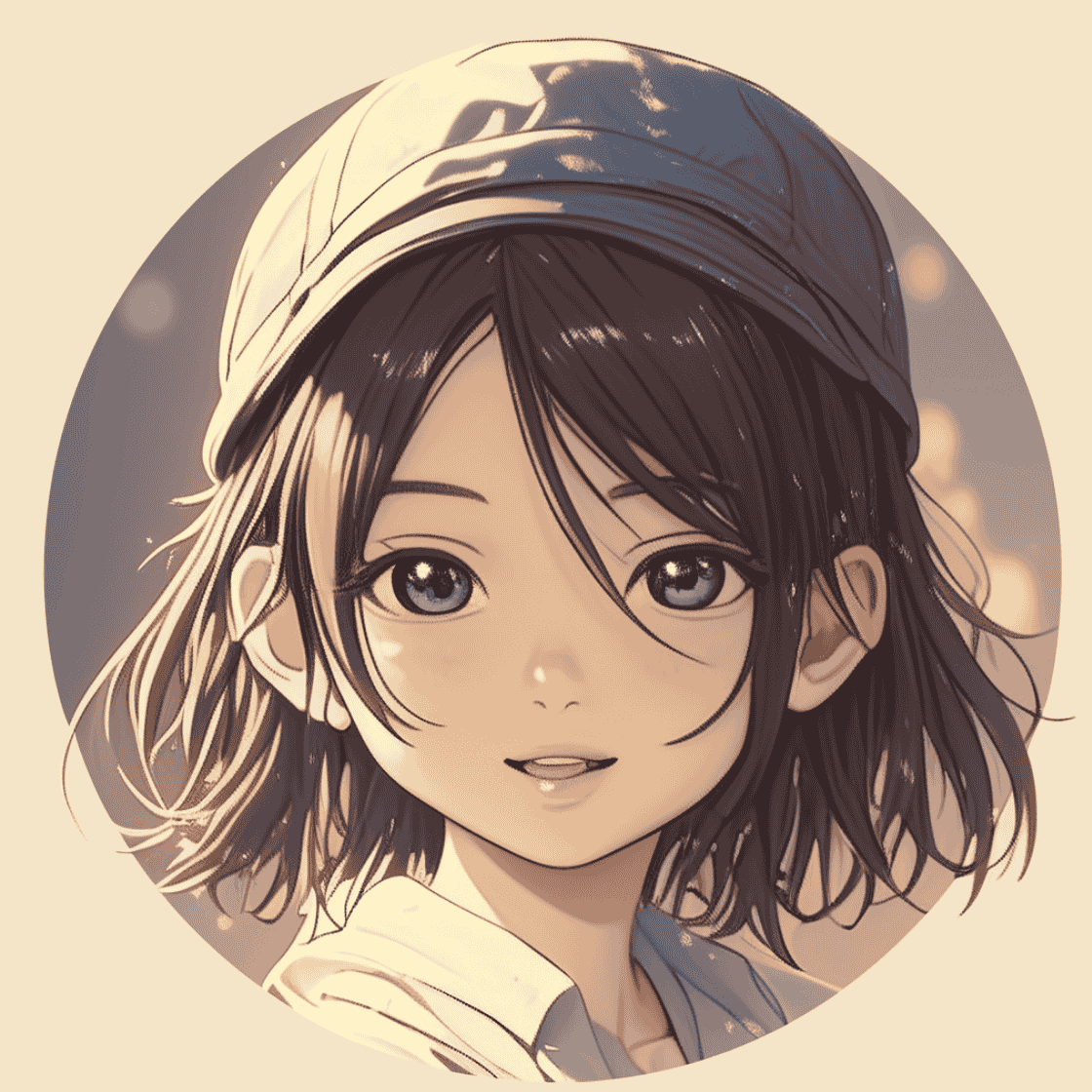
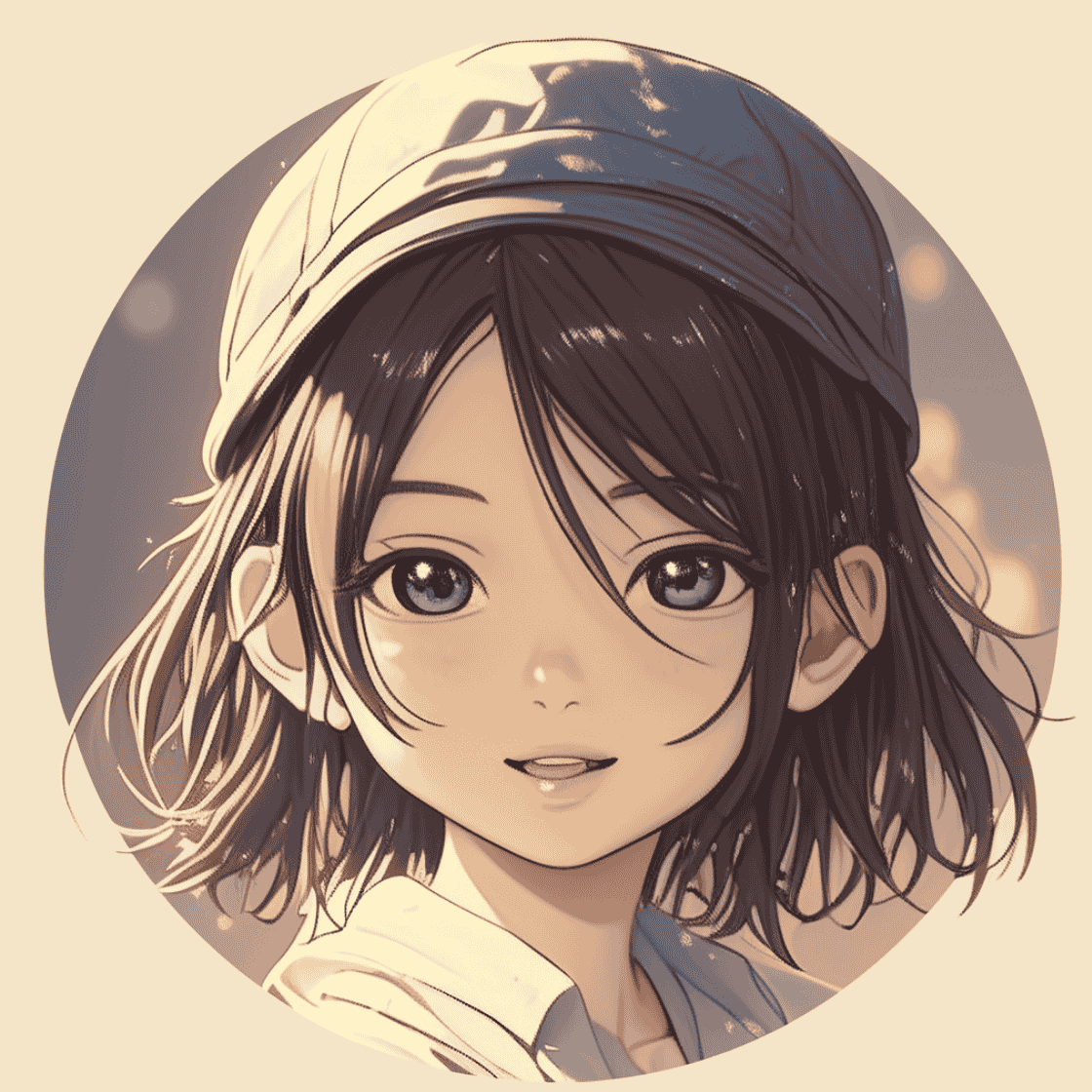
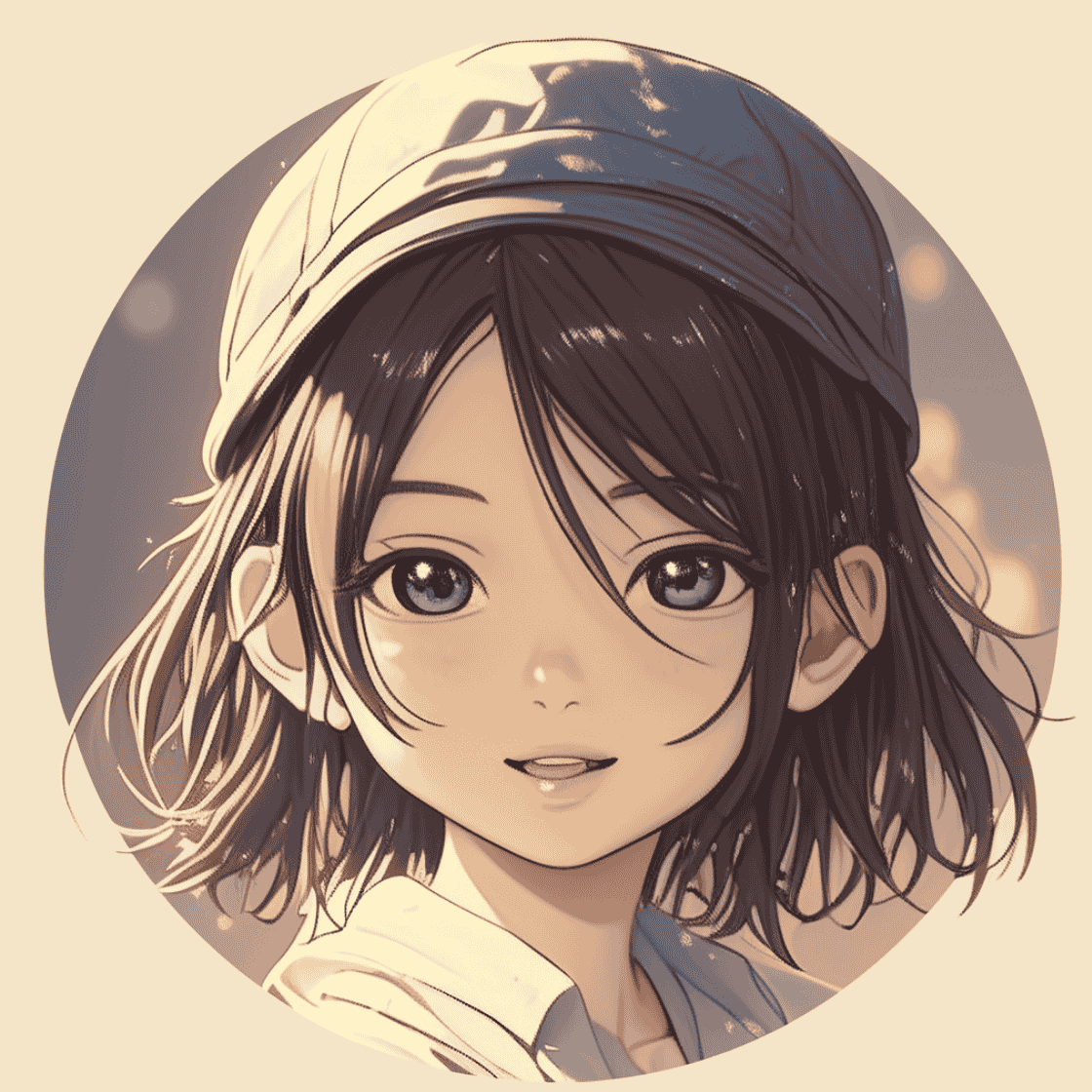
水質を維持するポイント
水質を良好に保つためには、適切な受水槽の設計と定期的なメンテナンスが重要です。具体的には、水の滞留を防ぐための構造的な工夫、定期的な清掃と点検、そして水質検査の実施が欠かせません。
また、受水槽の容量を建物の使用水量に対して適切に設計することも大切です。容量が大きすぎると水の滞留時間が長くなり、残留塩素の減少や水質劣化の原因となる可能性があります。
受水槽の清掃は法律で義務付けられている
受水槽の清掃は、建物の所有者や管理者の義務です。法律によってどのような規定があるのか見ていきましょう。
清掃の法的義務と頻度
受水槽の有効容量が10㎥を超える場合、その設備は「簡易専用水道」として水道法の規制対象となります。簡易専用水道の所有者または管理者は、年に1回以上の清掃を実施することが法律で義務付けられています。
清掃を怠った場合、最大100万円の罰金が課せられる可能性もあります。これは公衆衛生に直結する重要な問題だからこそ、厳しい罰則が設けられているのです。



清掃方法と流れ
受水槽の清掃は専門の資格を持った業者に依頼するのが一般的です。清掃の基本的な流れは以下の通りです。
- 事前準備と水質検査:清掃前の状態を確認
- 断水・排水:水槽内の水を抜く
- タンク内の清掃:壁面や底面の洗浄
- 消毒:次亜塩素酸ナトリウム溶液などによる消毒
- 拭き上げ:清掃後の水槽内を乾燥させる
- 水の補給:清掃完了後に水を再度満たす
清掃には専門的な知識と技術が必要なため、素人が行うのは危険です。必ず専門業者に依頼しましょう。
清掃費用の相場
受水槽の清掃費用は、水槽の大きさによって異なります。一般的な相場としては、清掃単体で数万円から数十万円程度。水質検査も一緒に行うことが多く、その場合は3,000〜10,000円程度の追加費用が発生します。
費用は高く感じるかもしれませんが、水質の安全性を確保するための重要な投資と考えるべきでしょう。健康被害のリスクを考えれば、決して高すぎる金額ではありません。



まとめ:受水槽と貯水槽の違いを理解しよう
ここまで、受水槽と貯水槽の違い、設置基準、仕組み、そして清掃管理について解説してきました。最後にポイントをまとめておきましょう。
「貯水槽」は水を貯める設備全般を指す総称であり、「受水槽」はその一種で、特に水道水用の設備を指します。受水槽は建物の給水システムの一部として、安定した水圧と水量を確保するために重要な役割を担っています。
また、受水槽には設置基準や清掃について法律で厳格な規定があり、年に1回以上の清掃が義務付けられています。これを怠ると罰金や健康被害につながる可能性があるため、建物の所有者や管理者は責任を持って管理する必要があります。
水は私たちの生活に欠かせないものです。その水の供給を支える受水槽について理解を深め、適切な管理を心がけることで、安全で快適な水環境を維持しましょう。



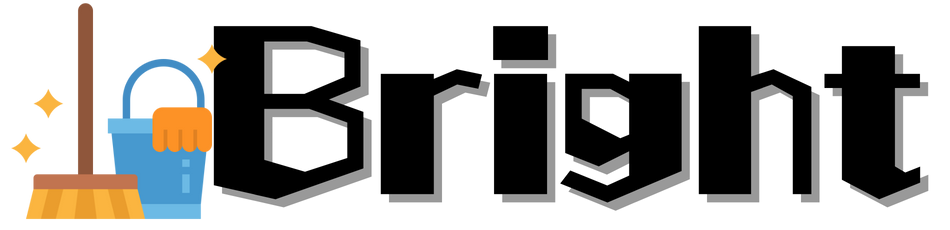

コメント